日本ラグビーフットボール協会
コーチングディレクター
中竹 竜二氏
インタビュアー
クライス&カンパニー 代表取締役社長
丸山 貴宏
キャリアコンサルタント
松尾 匡起


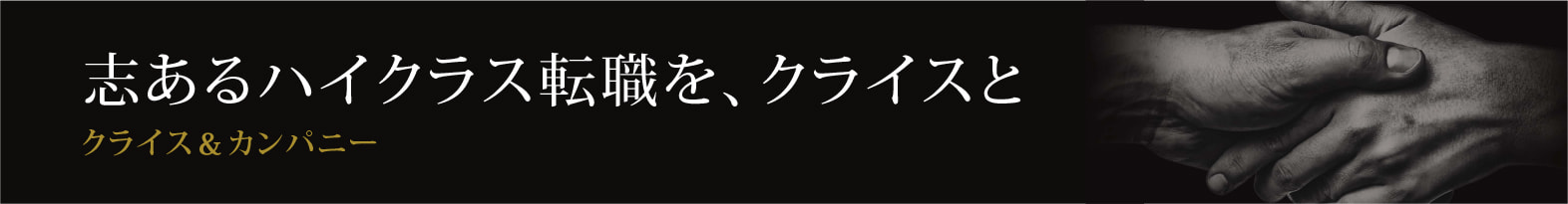










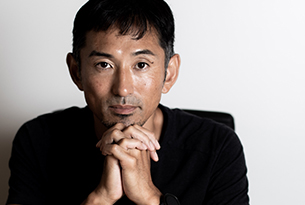








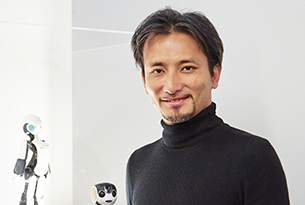













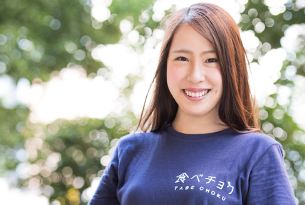



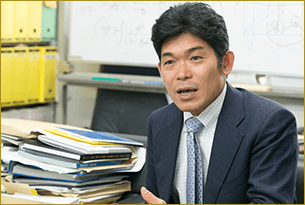

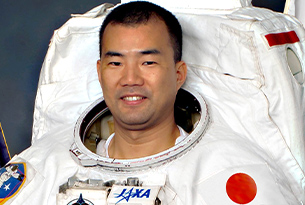






インタビューを終えて