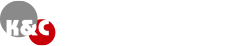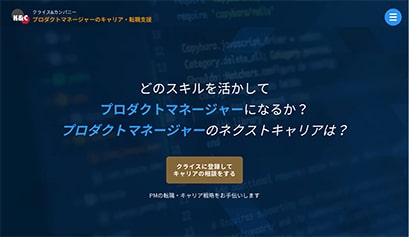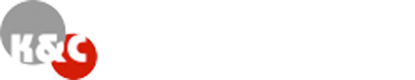企業からは「どうすればうまく面接ができるのでしょう」と聞かれますし、候補者からは「どうすれば面接で合格できるんですか?」と聞かれます。
さて、どうすれば双方にとって最高の面接ができるのでしょうか。
最高の面接とは、企業にとっては「自社で活躍してくれる人材を採用する」ことですし、候補者にとっては、「自分が最も活躍できてハッピーになる就職をする」ことができるような面接のことです。
言葉を変えれば「お互いがハッピーになるための確認」がしっかり出来る面接が目指すべき「最高の面接」です。
はたして今、そのような面接が行われているでしょうか・・・。
残念ながらほとんどの面接がその域ではありません。
では、その原因はどこにあるのでしょう。
一言でいうと、企業も応募者も「評価」に集中しすぎているのです。
面接である以上、当たり前だと思われるかもしれませんが、その前にやらねばならないことがあるのです。
まずは企業。
面接といってもそれは他人対他人のコミュニケーションの場です。
コミュニケーションの場である以上、まず、最初にやらなければいけないのは「関係構築」。
この人には話しても大丈夫だな、この人に自分のことをちゃんと分かってもらおう、と思ってもらうことが大事なのです。
いきなりの圧迫質問や不遜な態度は論外です。
そして、その次にやるべきことは、徹底した応募者への「理解」です。
一体目の前の応募者はどんな人なのだろう、を徹底的に追及することが大事です。
ここが曖昧、中途半端だと正しい評価はできません。
ここで都合のいい思い込みや、表面的な理解だけをしていると採用してはいけない人を採用してしまうということにもつながるのです。
面接官にはこの「理解」があって、はじめて応募者に対する正確な合否判断ができるのです。
関係構築⇒理解⇒評価。
この流れで面接をすすめて行くことが大切なのです。
それがいきなり「評価」しようとするから、面接がデタラメになってしまうのです。
一方、応募者。
応募者も面接官に評価されている、を前提に話をするので、「面接官によく思われたい」という力が働きます。
その気持ちが全てと言っても過言でなないでしょう。
結果、自分の思っていることよりも耳触りのいい一般的な答えをして、何も伝わらないということが起きてしまいます。
応募者は面接官に「よく思われる」ではなく「正しく理解してもらう」に目的を変えないと、どうにもなりません。 自分のことを正しく理解してもらって、面接官に同社で活躍できそうかどうかを評価してもらう。
こういう謙虚なスタンスで面接官の質問に答えていけば、なにも困ることはありませんし、極めてスムーズに面接は進行していくはずです。
またホントの自分を知ってもらわないと、内定もらっても、入社しても不安で仕方ないのではないでしょうか。
それを応戦モードで質問に隙なく答えて行こうとする、正しい答えを探す。
そんなことをしても面接官の応募者へ理解はちっとも進みませんし、理解のない中では合否も なにもあったものではないのです。
企業も応募者も「評価」ではなく「理解」に集中する。
そうすることで、双方がハッピーになる「最高の面接」が実現して、 活躍する個人が増えて企業が活性化して日本経済が元気になると思うのですがいかがでしょうか。
(2013年4月10日)
今回の教訓&アドバイス
「よく思われる」意識から「理解してもらう」意識へ転換。
故に本音と事実ベースで話をする。
応戦モードは厳禁。

キャリアのプロに相談してみませんか?
「もっと詳しい話を聞いてみたい」、「自分のキャリアについてアドバイスが欲しい」
等のご希望がございましたら、お気軽にご相談ください。
同じカテゴリーのバックナンバー
-
Vol.257 面接準備をシンプルに体系的に進める方法

皆さんは企業との面接に臨むにあたり、どのような準備をしますか?初めて転職活動をする方や紹介などで転職してきた方は、以下のような疑問や不安をもっている方が多いです。 ・スクリプトを準備し....
-
Vol.255 面接準備として、想定問答を暗記してはいけない理由

面接に臨むときに何を聞かれるか、聞かれたことにちゃんと答えられるかという不安はあるものです。そのため、面接での想定質問への回答を考えておく人もいるでしょう。今回は、想定質問に対する準備に....
-
Vol.252 強みを自覚していない人は意外に多い。強みの引き出しを増やす方法

「あなたの強みを教えてください」私が面談で、候補者さまに必ず質問することのひとつです。自己認知している強み、他者から言われる強みについてお聞きしたものの、答えがすぐに出てこないことは意外....
-
Vol.251 面接の再調整やキャンセルを、企業側はどう感じるのか

Aさんの転職活動を支援していたときの出来事です。Aさんの志望度が高い企業の書類選考を通過し、面接日程の調整にしている途中でAさんからの返信が数日きませんでした。その後、Aさんから面接日程....
-
Vol.246 面接後すぐに、キャリアコンサルタントと会話するメリット

我々キャリアコンサルタントが、サポートしている求職者の皆様にお願いしていることがあります。それは、企業との面接(カジュアル面談含む)の後に、できるだけタイムリーに感想などのフィードバック....