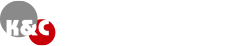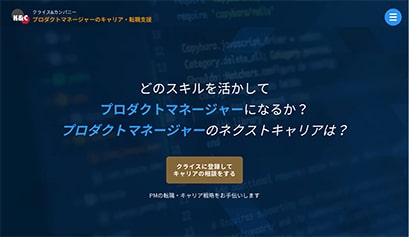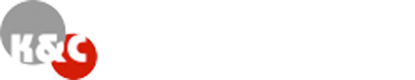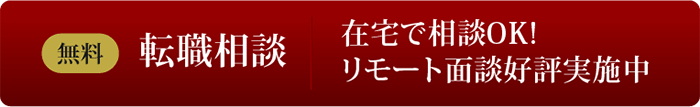お知らせ一覧
What’s New list

インターネット/Webビジネス業界における転職市場は、引き続き活況で、この勢いは当面続くといって良いでしょう。この転職市場の活況を牽引しているのは、DeNAや楽天、メルカリなどに代表されるような、所謂「メガベンチャー」の存在があることは言うまでもありませんが、Fintech、Edtech、Healthtechなどのように、〇〇×Technorogyといった世の中に新たなサービスを展開しているスタートアップ企業の積極採用が近年は特に目立っています。
この「スタートアップ企業の積極採用」の背景には、国内スタートアップ企業の資金調達額が2018年1~6月に1732億円(前年同期比4割増)と過去最高を更新するなど(※1)、スタートアップ企業への注目度が高まっていると同時に、投資が非常に活発であるということが言えそうです。(※1 日本経済新聞より)
Webビジネス・サービスを展開している企業に限らず、スタートアップ企業が資金調達を終えた後、満を持して取り組む最重要事項の一つが、更なるビジネスグロースに向けた幹部人材の採用です。
事業グロースを担う新規事業開発や事業開発推進の責任者、財務戦略を担うCFO、そしてサービスグロースには欠かせないプロダクトマネージャーやプロデューサー、さらにはTech系スタートアップの技術力の肝であり根幹を担うCTO、VPoEなど。経営者や経営陣とVisionを共にし会社の成長を一気にドライブすることを可能にする、高いビジネススキルと知見をもった幹部人材の採用ニーズが高まっています。
コンサルティングファーム出身者、特にインターネットビジネスに知見のある方のニーズは止まるところを知りませんが、ネット系メガベンチャーにて、スタートアップ企業がこれから直面する課題(もしくはそれに近しい課題)を過去に乗り越えてきたご経験とご実績のある方のニーズは極めて高い状況と言えます。こうしたことからも、やはりWebビジネス業界にて経験を積むことは、ネクストキャリアの幅がより一層広がることにつながると言えるでしょう。


年収ダウンのケースって?
年収ダウンでも転職成功?
年収がダウンしたにも拘らず転職は成功したとポジティブに捉えている方々の多くは、転職によって「やりたいこと(できなかったこと)ができること」をより価値のあるものと考え、新天地でのキャリアに大きな魅力と可能性を見出してワクワクしています。この「やりたいことができること」が指すのはまさしく十人十色。大きくいくつかに分けると、例えば、裁量が持てる、マネジメントができる、経営幹部になるチャンスがある、IPOのチャンスがある、といった「ポジション」を意識していることもあれば、これまでの経験がどこまで通用するか試すことができる、タフな環境で自身にストレッチをかける、キャリアの幅を広げられる、といった「成長」を意識していることなどが挙げられます。
その他にも大きなターニングポイントとなるような出会い・気付きがあったとき、例えば「人生を賭けてでも取り組みたいテーマと出会ったとき」や「この人と一緒に働きたい!!と心の底から思えるような経営者・上司・同僚と出会ったとき」、そして「人生の中で大切にしていること(家族や趣味など)に時間を使いたいと気付いたとき」などは、年収についてはほぼ度外視で転職を決断されています。
年収ダウンでも入社後活躍する人とは?
結論、年収ダウン=転職失敗と安易に決定づけるべきではなく、自身の転職をどう捉えるかが大事のようです。ちなみに、入口(入社時)の年収に過度な価値を置かない方は、入社後に活躍していることが圧倒的に多いです。それには色々な理由が考えられますが、「やりたいことができる」ことを優先して決断しているので、日々やりがいを感じながら仕事に取り組んでいることが、結果として成果・年収アップに繋がっているようです。逆に、入口でお金に強く拘った方が入社後に大活躍しているといった話は残念ながらをあまり耳にしません。周囲の期待は高くなり、相当なプレッシャーを自ら背負うことになりますし、もしかすると年収アップを優先した決断は、入社時点ですでに目的をクリアしてしまっているのでモチベーションが続きにくいのかもしれません。
最後になりますが、決して年収ダウンを推奨している訳ではありません(笑)。あくまでそれぞれの方にとってベストと言えるような転職をしていただきたいと思っています。そしてベストな決断をするにあたっては、入社時の一時の年収ダウンを一概に失敗と捉えず、転職によって叶えたいものを最優先にして決断し、楽しくて仕方がない日々を送って欲しいと思っています。
(2018年7月20日)
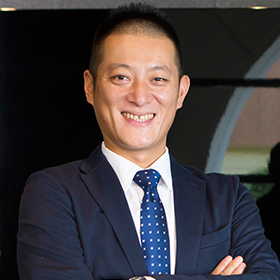

インターネット業界に限らず、各社が積極的にIT投資を行っており、IoTやAI、RPAなどの新しいテクノロジーや大規模なデータを活用した新たな事業やプロジェクトが次々にスタートしています。こうした背景もあって、データ分析や統計解析といったAIの周辺技術に明るいエンジニアは今まさに「引く手あまた」の状況です。
もちろん、インターネット業界では、エンジニア以外にもWebディレクターやマーケティング職、そして企画職に至るまで各社の採用ニーズは非常に高まっています。その中でも最近は特に、上述したAI、IoT、さらにはブロックチェーン・仮想通貨、VRといったキーワードに関連する新しいテクノロジーを活用した新規事業・新サービス開発、そして国内外問わず既存ビジネスのグロースを任せるようなビジネスサイドの求人ニーズが増えてきております。
このビジネスサイドの採用ターゲットとなるのは、Webサービス企業での経験者であるのは言うまでもありませんが、その他ではコンサルティングファーム出身者が相変わらず人気の高いキャリアとして注目されています。その中でも、IT投資が活発である昨今の市場を踏まえ、AI、IoT、ブロックチェーンなどに関連するプロジェクト経験のあるコンサルティングファーム出身者が即戦力人材としてより注目されています。
今後もさらに市場規模の拡大が見込めるWebビジネスにおけるキャリアは一昔前に比べて大いにそのプレゼンスを高めてきており、市場におけるその需要も高まっています。コンサルティングファームで活躍中の方にとって、新しいテクノロジーに触れる機会の多いWebビジネス関連プロジェクトにて経験を積むことは、ネクストキャリアの幅がより一層広がる良いチャンスになると言えるでしょう。

普段使っている言葉の意味が通じない?
面接の場では、共通言語は非共通言語
普段からコミュニケーションをしている人物と話す時の言葉は、最初は使用する人達の間でお互いの認識が多少ズレていても、コンセンサスをはかりながら、使われる度に徐々に修正されていき、遂にはその都度意味を加えたり細かな説明をしなくても、お互い理解し合える便利な共通言語へと成長していきます。この共通言語を醸成する関係性そのものはとても良いことではあると思うのですが、一方で、この共通言語によるコミュニケーションに慣れ過ぎてしまっている、もしくはその自覚がない場合、自身の身の回りの「外」にいる人とコミュニケーションをする際に苦労するだけでなく、本人が意図しない意味で相手に伝わってしまうリスクが生じることがあります。
世間一般で通用する共通言語のように思えても、使用するシチュエーションによって、それぞれが指す意味合いは違いますし、その言葉によって伝えたい意図も必ずしも一致する訳ではありません。例えば、「マーケティング」という言葉一つとっても、プロダクトマネジメント、プロモーション、ブランディング、さらにはインターネットマーケティングやダイレクトマーケティングなど、「マーケティング」が指すものはまだまだあります。これら複数の意味を持つ言葉が、ある環境内で使用される際、いつしか「あるものを指すときに使い、それで皆が理解できる」共通言語になっていることがあるのです。
では、このことを意識せずに面接に臨んでしまった場合、どのようなことが起こるのか?面接の場は、その言葉の持つ意味や背景など「詳しい説明の必要がない共通言語で理解が得られる環境」ではありません。よって、会社では問題なく通じていた言葉が面接官に伝わらない。となると、理解を得るためには説明が必要。しかし、この詳しい説明など必要ないコミュニケーションをしてきているため、いざ人に説明するとなると・・・、どうしよう。。ということが起こるかもしれません。
相手は「何でも知っている訳ではない」という前提で準備する

インターネット業界における転職市場は引き続き活況で、この状況はまだまだ続くと言っていいでしょう。
Webエンジニアはもちろん、Webプロデューサー・ディレクターから、営業・マーケティング、企画職に至るまで、ほぼ全ての職種において採用ニーズが高まっていますが、その中でもここ数年は特に、データサイエンティストやデジタルマーケティングといったキーワードにかかわる人材の採用が活発化しています。
その背景には、各企業が蓄積しているビッグデータの分析とその活用に焦点が当てられていることが挙げられます。IT技術の発展により、以前と比較して容易に大規模データを蓄積することが可能になり、また、データ処理を行なうための整備・機器性能も格段に向上しています。
かつてはその扱いに試行錯誤を繰り返していた膨大なデータも多くの企業が取り扱えるようになり、また、各社その膨大なデータをビジネスの現場でさらに活かすべく、いかに事業成長や商品・サービス企画に有効活用するかといったことに力を注いでおり、その課題解決のための中心的な役割を担う人材として、データサイエンティストやデジタルマーケティング担当者に注目が集まっています。
ビッグデータを活用したマーケティングは昨今のビジネストレンドとなってきていますが、データサイエンティストとしてのキャリアを積み重ねている方そのものの数はまだ少ない為、統計学とITスキルを有し、データを扱う仕事の経験を活かしてデータサイエンティストへのキャリアを目指す方にとって、現在の転職市場は「売り手」市場と言えるかもしれません。
また、「データサイエンティスト」が担う仕事内容においてもまだまだ明確な定義はなされていない状況でもあるので、自身の活躍次第で職種そのものの価値を高め、課題を解決し、社会・会社の利益に大きく貢献できるというやりがいも味わえる大きな可能性を秘めた職種であるとも言えるでしょう。

報告内容と結果が一致しない?
面接に臨むスタンスで結果が変わる
今一度「面接の場」では何が行われるかを理解して臨む
「面接は面接官と応募者がコミュニケーションを取り合い、その人がその会社に合っているかどうかを互いに確認し合う場」(※①)と面接官は考えています。面接官が聞きたいことに応えていないばかりか、聞いていないことばかり話してしまっては、そもそものコミュニケーションが成立しません。面接官の質問の意図を理解し、熱意と誠意をもって、コミュニケーションしていくことを心掛けましょう。そうすればきっと良いご縁が生まれてくるはずです。
※①:弊社代表著書「そのひと言で面接官に嫌われます」より引用
(2017年6月20日)

インターネット業界における転職市場は引き続き活況で、大手から中小・ベンチャーに至るまで、各企業優秀人材の獲得のために様々な工夫を凝らし、これまでにも増して積極的に採用活動を行っています。
リファラルリクルーティングやダイレクトスカウト等の採用手法はもとより、現代の多種多様な働き方を推奨するための環境の整備(リモートワーク・福利厚生の拡充等)や、それらにまつわるあらたな人事制度構築、更にはSO付与といった待遇面の改善など、各社「優秀人材獲得のために、採用競合に負けまい」と他社との差別化を図るべく、ありとあらゆる策を練って努力しているような状況です。
インターネット市場そのものでみると、キュレーションメディア問題といった世間を騒がせたニュースはあったものの、インターネットメディアやSNSは引き続き市場を拡大しており、中でも最も市場規模が大きいECサイトは確実にそのシェアを拡大しています。その背景には、スマホ・タブレットの普及はもちろん、UI・UXの進化やリコメンド機能の向上が格段に進んでいること、そして、BtoB、BtoCだけでなくCto(Bto)Cなどを含めると、今やEC上で買えないものはないと言っても過言ではないほど商品ラインアップが多岐にわたり、しかも拡充してるため、インターネットを介した購買行動がより加速しているということが考えられます。
こうした状況から、エンジニア・Webディレクターから、営業・マーケティング、企画職に至るまで、ほぼ全ての職種で各社積極採用をしていますが、その中でも、AI・ビッグデータにまつわるエンジニアやデータサイエンティスト、そして、他業種とのアライアンスやM&Aの推進や新規事業開発をお任せできる人材や越境ECなどグローバルで活躍を期待できる方などを特に積極的に採用しています。
インターネット業界でキャリア構築していきたい方にとっては、今はとても良い環境であると言えます。