キャピタリストも起業家マインドを持ち、技術をビジネスへと橋渡しできる
まずは、ファストトラックイニシアティブ(FTI)を代表パートナーとして率いる安西さんのご経歴を教えていただけますか。
ベンチャーキャピタリストとして活躍する場として、数あるVCの中から安西さんがFTIを選ばれたのは、どのようなお考えからですか。
安西
前職でVCという業種を深く知ることになったきっかけが、このFTIでした。FTIは大学との産学連携に加え、大学発のシーズのスタートアップによる育成という先進的な取り組みを行っていました。現在も我々が行っている「カンパニークリエーション」、すなわち新しい企業の立ち上げをVCが主体的に進めていくという事業化モデルに2005年当時から積極的に取り組んでいたんですね。私はそれまで、VCはスタートアップ側から多くのアプローチを受けて投資先を選定し、実行した後は「果報は寝て待て」というスタンスだと思っていました。ただFTIはまったく違っていて、有望な技術シーズの育成に向けて丁寧に研究者を支援し、しかも事業化を構想する段階から関わっていく。そうしたアントレプレナー的なマインドを持って投資先に向き合っていくことに大いに惹かれました。私自身、コンサルティングで培ったビジネススキルを活かして起業する、という選択肢もあったのですが、FTIなら「こんな企業を創って、社会に発信していきたい」という自分の思いをVCの立場から叶えられると考えて参画した次第です。
パートナーを務められる原田さんは、どのようなご経歴でいらっしゃるのでしょうか。
原田
私も安西と似た経歴です。東大の大学院でRNAの研究に取り組んでいました。私は科学の面白さに魅せられていて、未知のデータに触れて新しい知見を導き出した時の興奮とか、そうした感覚を常に味わいたいという気持ちがベンチャーキャピタリストになったいまでも私の原動力になっています。卒業後はマッキンゼーに入社し、大企業の経営戦略立案や新規事業開発などのプロジェクトに関わりましたが、その時も科学によるイノベーション創出に携わりたいという思いをずっと抱いていました。ビジネスの観点からイノベーションを起こせる仕事は何かと考えた時、次のキャリアとしてVCが見えてきたんですね。ただ、VCに進む前に自分のスキルセットをもう一段階伸ばす必要があると考え、MBA取得のためにシカゴにあるビジネススクールに留学。そこで米国の大手VCであるARCH Venture Partnersで働く機会を得て、ベンチャーキャピタリストとしてしばらく経験を積んだ後、2019年にFTIに参画しました。
原田さんがFTIにご入社されたのは、どのような経緯なのでしょうか。
原田
米国のVCで投資業務に携わって感じたのは、いまやスタートアップはグローバルで戦わなければ成功できないということ。特にライフサイエンスの領域では、起業時から世界を見据えて、グローバルでどのように医薬品を創り、どのように市場を開拓していくかを考えて事業を展開していかなければならない。一方で自分のキャリアを考えた時、日本との接点も大事にしていきたいと考えていて、日本における強みがありながらグローバルマインドを持っているVC、そして私が究めたいライフサイエンス領域で実績のあるVCを探った時、真っ先に名前が挙がってきたのがFTIであり、ぜひここに参加したいと志望したのです。

深い技術的洞察とカンパニークリエーションにより、自ら先端領域を切り拓く
VC業界における御社の特長を教えていただけますか。
安西
我々は“Capital for Life”という企業理念を掲げ、「いのち」と「くらし」にフォーカスした投資活動を行っていることがまず大きな特徴です。具体的には、バイオテック、ヘルステック、メドテックの3領域を手がけており、これらの分野で20年以上にわたって豊富な経験を積み重ね、強固なネットワークを築き上げています。さらに、我々の投資先数は設立20年で40社強しかなく、平均すると1年に2社程度です。「いのち」や「くらし」に大きなインパクトをもたらす可能性を秘め、グローバル市場で評価されるポテンシャルを持った技術・事業シーズであるかどうかを、深くアセスメントすることで投資先を厳選しています。投資先に対して責任ある立場で、深く関わっていることも我々の特長で、約40社のうち16社は、我々自身が主導して設立、もしくは設立を支援してシード投資した企業であり、先ほどお話しした「カンパニークリエーション」の賜物です。成功に向けて起業家や投資先と伴走するキャピタリストとしてのスキルやマインドに加え、自ら先進的な領域を拓くアントレプレナーとしての気概も併せ持っていることもFTIらしさだと思っています。
いまお話いただいた「カンパニークリエーション」について、どのように投資対象に関与していくのか、具体的にご説明いただけますか。
安西
VCが主導する「カンパニークリエーション」は特にバイオ系などのディープテックスタートアップ投資で盛んに活用されるようになってきました。mRNAによる新型コロナワクチン開発で一躍有名になったモデルナも、もともとは米国のVCのフラッグシップ・パイオニアリングの「カンパニークリエーション」によって生まれた企業です。これは端的に言えば、VCが主導して研究者と一緒に新しい会社を立ち上げていくこと。たとえば、世の中を変えてしまうようなポテンシャルを秘めた発見があったとしても、当初はビジネスとして投資できるような状況ではないケースがほとんど。そこで、その独創性の高いアイデアや技術を生み出したアカデミアの研究者の方にアクセスして、「こんなデータが必要なのでは」などと起業に向けた研究開発計画について対話を重ね、さらにどんな知財ポートフォリオを組むべきか、どんな企業とパートナーシップを結ぶべきか、どんなマネジメント人材が必要かということを徹底的に議論し、事業計画を具体化していく。こうしたプロセスをVCが主導し、グローバルに発展しうる準備を進めた上で起業するのが「カンパニークリエーション」であり、米国のVCの一部では一般的な手法として定着しています。
「カンパニークリエーション」は、技術の実用化の成功確率を高める手法なのですね。
安西
ええ。先ほど名前を挙げたフラッグシップ・パイオニアリングなど米国の有力なVCは、水面下でかなりのリソースを投じて数多くのインキュベーションプロジェクトを推進し、その中から本当に勝算のある技術、医療を革新する可能性の大きな技術をセレクションして新たな企業を立ち上げています。ですから、ステルスモードを解除したときには、すでに十分に練り上げられた事業モデルを有しており、有力なマネジメントチームや投資家のシンジケートも抱えていて、成功確率の高いスタートアップになっています。
FTIさんが「カンパニークリエーション」を多数実施できているのには、何か秘訣というのはあるのでしょうか?
安西
このアプローチを、我々は日本において20年前から追求してきました。国内にも、グローバルに展開できる有望なシーズをお持ちの大学の研究者は多くいらっしゃって、そうした先生方と一緒に我々が主導して起業することにも数々挑戦しています。その過程には大きなリソースを要するのですが、我々はEIR制度のような形で事業立ち上げの経験や能力を有する人材をプールし、「カンパニークリエーション」にあたって最初からCxOとして経営に参画していただける方も抱えており、Day1から強力な企業としてスタートできる体制も整えています。

20年の経験と信頼の蓄積。いま、チームの力で、グローバルな投資支援を強化
原田さんは、FTIの特長や強みをどのように捉えていらっしゃいますか。
原田
先ほど安西がお話しした通り、VCとしての経験値が非常に高いことが大きな特長だと思います。FTIは創業して20年になりますが、20年ものスタートアップ投資歴を持つVCというのはそうは存在せず、長年にわたってロバストなネットワークを築き上げていくことは、グローバルでもゆるぎない勝ちパターンになる。米国には半世紀にわたってVCを営んでいるファームが数々あり、20~30年のキャリアを持つベンチャーキャピタリストもたくさんいます。この世界は、やはり豊富な経験を積んで業界内にネットワークを持っていることが圧倒的な強みになるんですね。いま私はFTIのボストンオフィスに在籍していますが、向こうで活動していると、現地のキャピタリストたちは「人」を見ていると強く感じます。いま付き合おうとしている人間は、どのようなバックグラウンドを持ち、どのような経験値があり、どのように案件に貢献できるのかをしっかりと見極めている。VCが信頼の上に成り立っているインダストリーだからこそ、「人」に対するこだわりが強く「一緒に仕事がしたい」と相手に思わせるためには、経験に裏付けられた知見やネットワークを提供できるかどうかが大切。FTIはその経験の蓄積が豊富であり、グローバルで存在感を示していく上で、日本の他のVCよりもはるかにアドバンテージがあると感じています。
原田さんはいまボストンにいらっしゃるとのことですが、御社ではグローバルで連携しながら投資活動を進めていらっしゃるのですね。
安西
そうです。FTIは2019年にボストンに拠点を開設しましたが、その前年に私はMITの短期のAdvanced Management Program(AMP)に参加し、そこでの経験が米国進出を決断させるきっかけになりました。現地でボストンのスタートアップやVC、大学関係者と対話する機会を得て、お互いに情報を流通させることでコミュニティの価値を高めている様子を目の当たりにしました。ここにアクセスできる立場でなければ当社自身が「ガラパゴス化」してしまい、グローバルへの橋渡しもできなくなると危機感を覚えたのです。ちょうどそのタイミングで原田が参画してくれることになり、ボストンオフィスの立ち上げを彼に託しました。我々にとっては未知の挑戦でしたが、この5年ほどで現地におけるFTIのプレゼンスは着実に高まりつつあり、大きな手応えを感じています。
原田
ボストンのチームも充実してきており、現在では日本と米国のスタッフが常に連携しながら投資先を支援しています。投資先のデューデリジェンスも日米のメンバーがミックスして実施し、起業家との面談も必ず両側のメンバーが参加し、共通理解のもとで議論を重ねて意思決定しています。さらに、その後の事業化を支援していく際にも、日本は日本、米国は米国で完結するのではなく、それぞれのネットワークを活用しながら必要なリソースを提供し合い、最適な資金調達や市場開拓などを実行。こうして日米のナレッジとネットワークを融合させることで、我々は他のVCとは次元の異なる支援ができると自負しています。
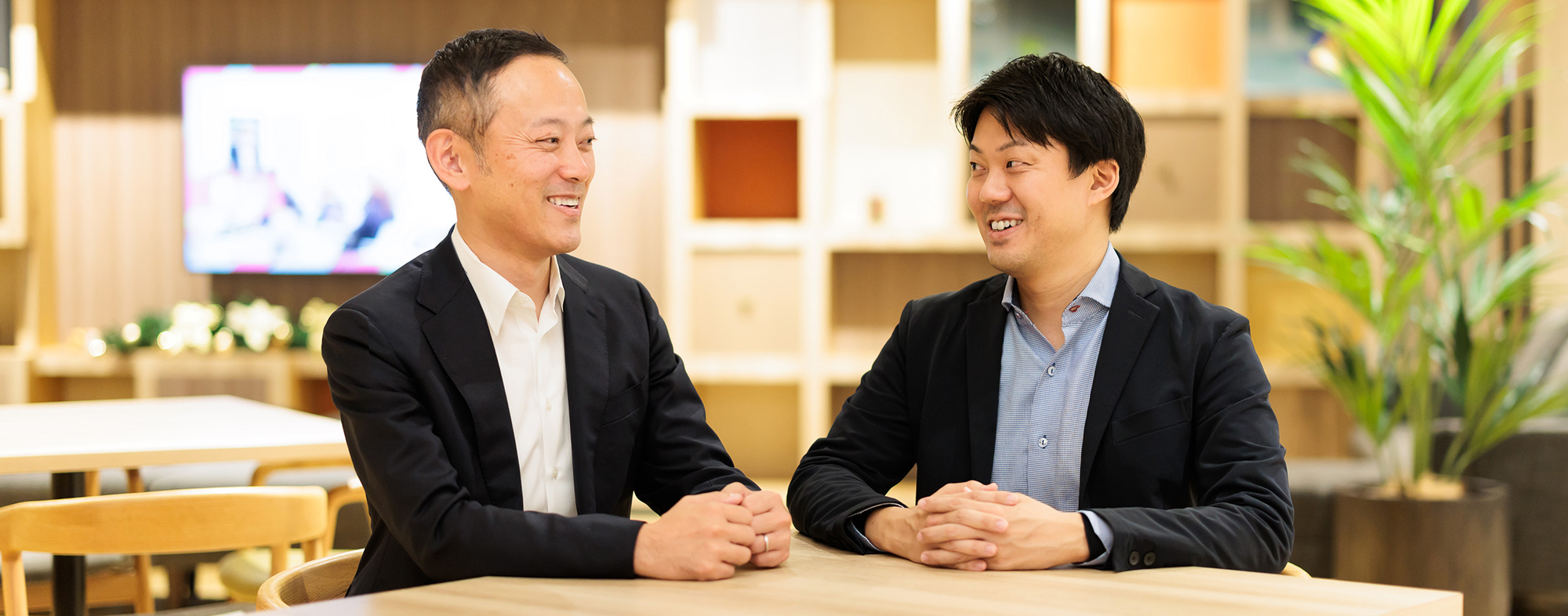
「セルフドライブ」と「コラボレーション」ができる方に参画してほしい
安西さんにおうかがいしますが、これからの日本のVC業界において、FTIはどうあるべきだとお考えですか。
安西
いま日本では、新たなVCが次々と立ち上がっており、投資先の価値を最大化するためのアプローチも多様化しています。そんななか、特にディープテック領域に携わる我々としては、スタートアップを一緒に支援する方々の裾野を拡げつつ、さらにVCとしては専門特化していく、という二つの方向で進化を遂げなければと考えています。裾野を広げるという点については、重大な社会課題の解決に取り組むスタートアップや起業家に対して、他のVCや金融機関の方々や、一般投資家の方々から深い共感を得る必要がある。その共感の輪を広げていくためにも、社会や医療現場にも大きなインパクトやベネフィットをもたらす成功事例を次々と作って発信していかなければと思っています。また、専門特化していくことも重要であり、たとえば「ライフサイエンス×AI」というように、いまや世界の最先端は革新的なテクノロジーの掛け算から生まれています。ですから我々自身も「いのち」と「くらし」を専門の軸としつつも、掛け算となる最先端領域の学びを深め、ネットワークを広げていくと共に、提供できる価値を最大化しなければと考えています。
そうした環境のなか、どのような人材が御社にフィットするのか、お二方の見解をうかがえますか。
安西
我々が掲げる“Capital for Life”の理念に共感し、切実な社会課題へのソリューションを医療現場や患者さんに一刻も早く届けることに意義を感じる方。そして、そのソリューションをもたらすイノベーションを社会に発信したいと熱望する方がFTIにフィットするのではないでしょうか。加えて、我々は投資先のスタートアップと一緒にグローバルな市場に挑戦したいと考えており、その志に共鳴していただける方。大きなポテンシャルを秘めた日本の技術の価値を、グローバルコミュニティのなかで認知を広げ、さまざまな投資家や企業の関心を惹きつけながら、社会実装につなげていく。それを担えるような、強いイニシアティブを持った主体がいまの日本には圧倒的に足りないと感じており、自らその役割を務めることにやりがいを感じるような方に参画していただきたいです。
原田
我々の究極のミッションは、投資を通じて次のフロンティアを創り、フロンティアを拡げていくことだと考えています。そのためには一人一人がユニークでなければならず、アントレプレナーのマインドを持っていなければならない。そこには二つの資質が大切であり、ひとつはセルフドライブできること。自分なりの仮説を立て、自らの考えで検証していく、そうした姿勢がフロンティアを拓いていくのだと思います。そして、もうひとつはコラボレーションできること。我々が実現したいことは、けっして一人では成し遂げられません。いろんな人の力を引き出すことで社会に大きなインパクトをもたらしていく、そんなアクションをおのずと取れる人と一緒に仕事ができればと思っています。
最後に、御社に興味をお持ちの方に一言メッセージをお願いします。
原田
FTIは、新しいことにチャレンジしたい方にとっては絶好の環境だと思います。VCとしてのスタンスもそうですし、社内もメンバー一人一人に新しい挑戦を促して任せていく文化です。自分が叶えたいことを徹底的に追求できる場ですので、志のある方にぜひ仲間になっていただきたいですね。
安西
新しいサイエンスと常に接して、社会にどう発信すればイノベーションに結びつくのかをクリエイティブに考え、多くのステークホルダーとの繋ぎ役を果たして、社会を変えていくような大きな流れを創り出していく。そんな我々の仕事は本当にやりがいに溢れています。これから参画いただく方には、最大限成長できるような機会やチャレンジの場をご提供できる自信もあります。ぜひFTIでのキャリアを積極的に検討していただければと思っています。








安西
私はもともとアカデミアを志向していましたが、東京大学の大学院で分子生物学の博士号を取得した後、コンサルティングファームのアーサー・ディ・リトル・ジャパンに入社しました。東大在籍中、自分が取り組んでいた基礎研究の中から知財化できる種が見つかって、それを産業界に橋渡ししていく、いわゆる産学連携に関わることがあったんですね。そうした経験から、アカデミアの「知」をビジネスに繋げていくことをライフワークにしたいと志しました。一方で橋渡しする難しさを痛感したこともあって、まずはアカデミアとの対岸となるビジネスの世界を理解しようとコンサルティングファームに入社しました。そこでベンチャーキャピタリストという役割に出会い、まさにこれこそ自分の天職だと。そして2006年にFTIに参画し、以来20年近くキャピタリストとしてキャリアを重ねています。