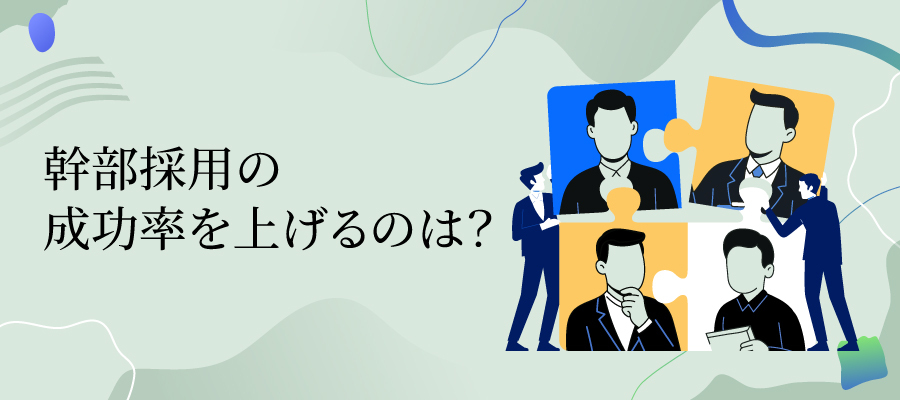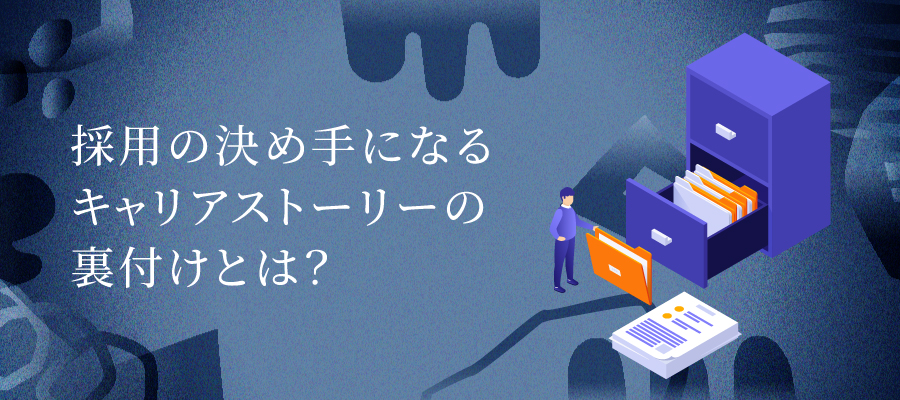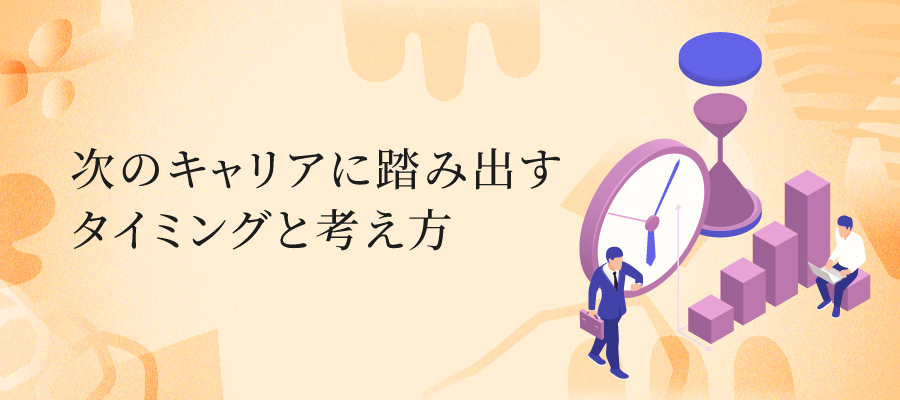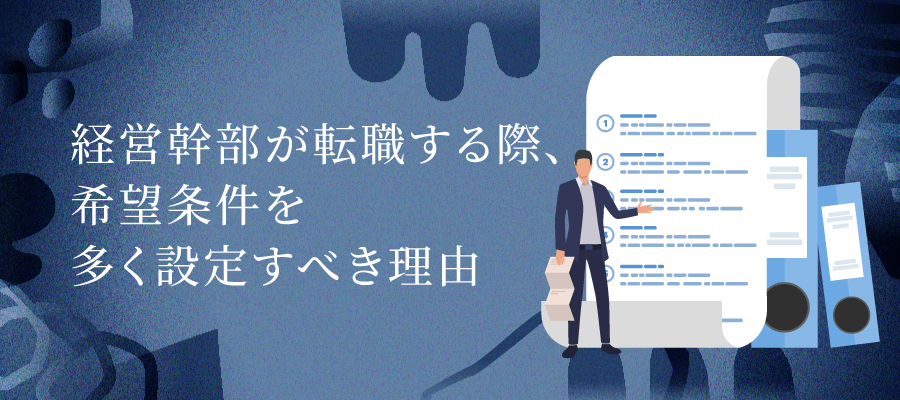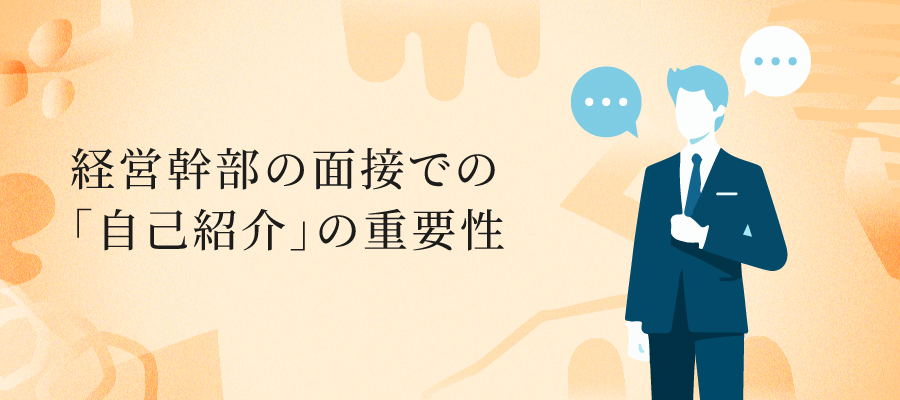経営幹部の採用をお手伝いしていると、どんなに慎重に進めても、残念ながら一定数は「成功した」と言い切れないケースに出会います。幹部クラスの採用は、企業にとっても個人にとってもインパクトが大きく、成功・失敗の差がその後の事業やキャリアに長く影響を及ぼします。今回は、そうした幹部採用の「成功確率」を少しでも高めるための考え方について、いくつかの視点から整理してみたいと思います。
まず、個人がすべき「自己開示」と「自己理解」
幹部人材は、過去に所属した企業で高い成果を出してきた方々ばかりです。いわば“実績のある優秀な人材”であるにもかかわらず、新しい環境で思うように力を発揮できないことがあります。その原因の一つは、「自分の得意・不得意を正確に言語化できていない」ことにあります。
キャリアが長くなるほど、強みと弱みは自覚しているはずです。しかし実際には、不得手な領域をどのように周囲に共有するかに戸惑う方が多いのも事実です。ところが、不得手を隠すことはマイナスではなく、むしろオープンに伝えることで誠実さや信頼感を得られるケースが少なくありません。完璧な人はいません。自分を「正しく見せる」よりも、「正しく伝える」ことの方が、結果として良いマッチングを生むのです。
企業側がすべき「要件定義」と「課題の明確化」
一方で、企業側も「今回の幹部採用で、何を解決したいのか」を明確にしておく必要があります。経営課題が曖昧なまま「優秀な人が来てくれたら」と採用を進めると、入社後に方向性のズレが生じやすくなります。採用要件の定義とは、スキルセットや経験値の確認にとどまらず、「どんな思想や価値観を持つ人が、現経営陣と一緒に走れるのか」を具体的に描くプロセスでもあります。
今回は特に大事な3つの観点を以下に挙げたいと思います。
1. フェーズの違いを見極める
スタートアップ、メガベンチャー、大企業(いわゆるJTC:伝統的大企業)、そして外資系。それぞれのフェーズや企業文化によって、求められるマネジメントの型は大きく異なります。
・スタートアップでは「ゼロから仕組みを作る」「意思決定を高速で回す」能力が重要で、組織やルールが未整備なカオス環境を楽しめるタイプがフィットします。
・メガベンチャーでは「混沌から秩序への移行期」をリードできる柔軟性が問われ、オペレーションと戦略の両輪をバランスよく回せる人材が求められます。
・大企業では「組織を動かす」力、すなわち根回し・調整・合意形成といった政治的感度が成果を左右します。
・外資系では「結果に対する説明責任」と「明快なロジック」が重視され、エグゼキューション能力とスピードがものを言います。
どのフェーズでも万能なリーダーはいません。大切なのは、「自分がどのステージ・環境で最も力を発揮できるのか」を本人・企業双方が理解していることです。
2. アドバイザー側と事業会社側のギャップを理解する
次に、アドバイザー側(コンサル・投資銀行・ファンドなど)と事業会社側の経験の違いです。
アドバイザー出身の方は、構造化・分析・提案といった思考の精度が高く、経営課題を整理する力に長けています。ただし、事業会社に移ると「意思決定を下す側」「実行責任を負う側」に立つため、スピード感や泥臭さ、社内調整のリアリティに戸惑うことがあります。
一方、事業会社出身者は「現場で結果を出す」ことに強みを持ち、メンバーの育成や実行フェーズの粘り強さに長けていますが、プロフェッショナルファーム出身者と比較すると、専門性や様々なケース事例のナレッジなどにおいて見劣りするケースもあります。
このギャップを埋めるには、「どちら側の経験を活かして、どの領域で付加価値を出すのか」を明確に言語化することが大切です。企業側も、単に“有名ファーム出身”という肩書きではなく、「実務でどう機能するか」を見極める必要があります。
3. カルチャーフィットと経営層との相性
幹部採用で最も難しいのが、カルチャーフィットと人間性の相性です。スキルや経験が十分でも、価値観や意思決定スタイルが噛み合わなければ長続きしません。
最近では、オファー前後にフォロー面談や会食を設定し、相性確認のプロセスを丁寧に設ける企業が増えています。それでもなお、ミスマッチはゼロにはなりません。その一つの解決方法として、NDAを結んだ上で経営会議に参加させてもらうという手段があります。
会議では、社長や役員の発言のトーン、議論の深度、メンバー同士の関係性や立ち位置、そして互いへの配慮のバランスなど、言語化しづらい「空気感」が見えてきます。実際に経営会議に参加させてもらえる事例はスタートアップに多いですが、参加が難しい場合でも、会食などでお互いに打ち解けてきたタイミングで、経営会議の雰囲気を聞いてみるのも良いかもしれません。
最後に ― ミスマッチを減らすための“問い”
結局のところ、転職も採用も「入ってみないと分からない」側面は残ります。ただし、ミスマッチを一定減らすことは可能です。
個人側は、「自分はどんな環境で最も力を発揮できるのか」「どんな経営者となら腹を割って議論できるのか」を自問する。企業側は、「この人を迎えたあと、どんな未来を描きたいのか」を具体的に言語化する。その“問い”の精度が、採用成功の確率を大きく左右します。 経営幹部の採用は、企業の未来を左右する経営判断のひとつです。そして同時に、個人にとっても人生の大きな転機です。選考プロセスが進み、個人側も企業側も気持ちが高まると冷静さを失いがちです。だからこそ、どちらも一歩立ち止まって慎重に判断することが大切だと思います。最終意思決定の段階で少しでも迷いや違和感があれば、遠慮なくご相談ください。冷静な第三者の視点で、最適な判断をサポートさせていただければと思います。