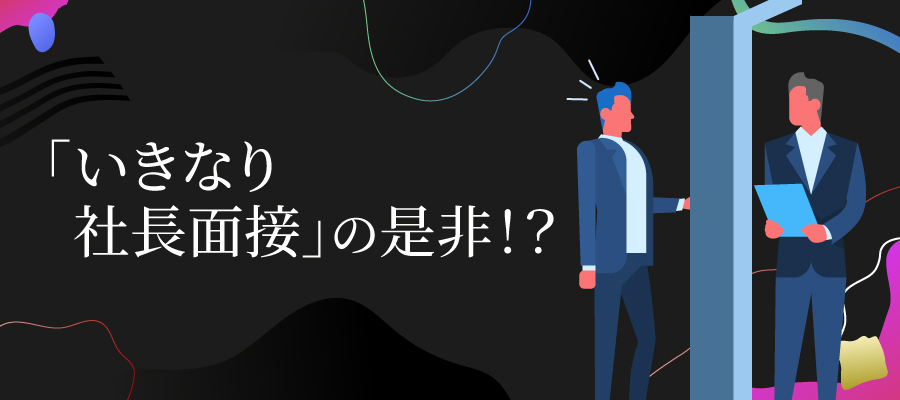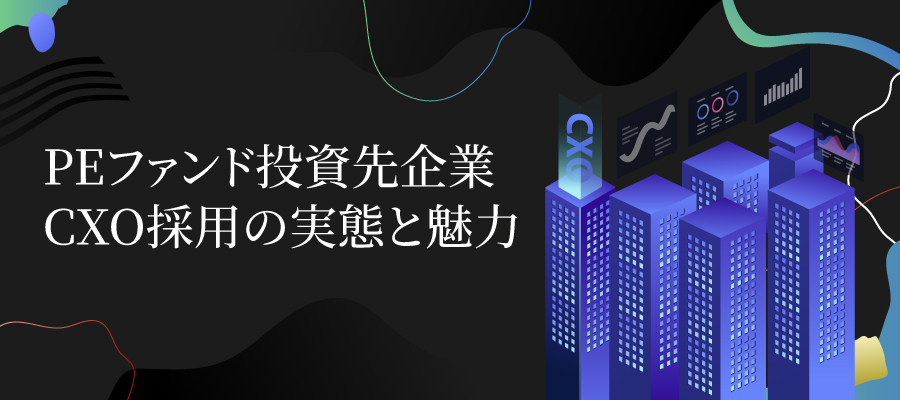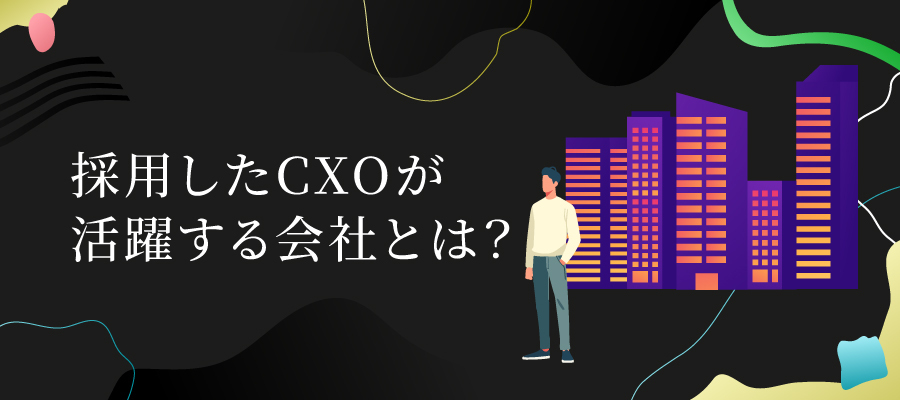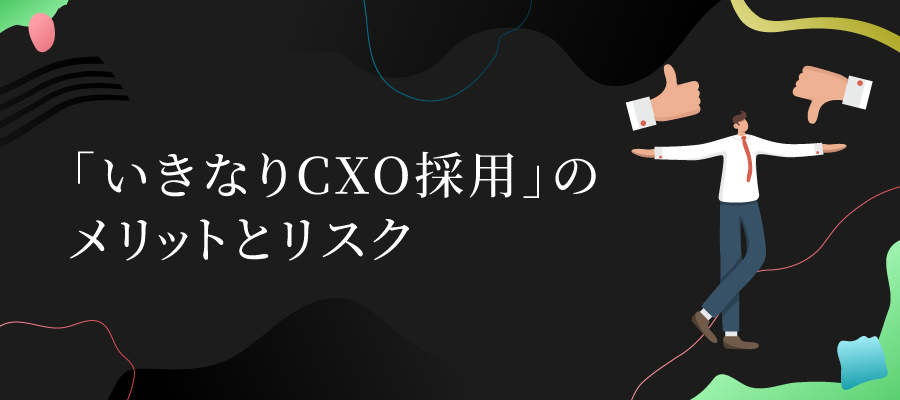経営幹部採用の成否を分ける「アトラクト」
CXOを始めとする経営幹部採用でうまくいっている会社は、経営者及び経営陣のコミットメントが強く、通常とは異なる採用プロセスを取り、初回面接に社長自ら臨む会社もあります。これは以前の記事でもお伝えしました。
私たちはこれまでのコラムでも、CXOクラスの採用において、初回の面接からCEOが登場することが、企業の本気度を候補者に強く伝える上で非常に有効であるとお伝えしてきました。実際、スタートアップやPEファンド投資先など、スピードと熱量が求められる企業では特にその傾向が強く見られます。
また、メガベンチャーや時価総額数百億円規模の上場企業でも、最初の面接からCEOが出てくるケースが増えています。CXOクラスの採用に強くコミットするCEOが増えていることの現れでしょう。
ただ一方で、すべての企業において、最初からCEOが出てくることが必ずしも良いとは考えていません。その理由は「アトラクト」(候補者の関心を引き、入社への意欲を高めること)にあります。会社によってはCEOが候補者に対するアトラクトが得意とは限らず、他に適任者がいる場合が少なからずあるからです。
そのため、会社によっては最初の面接でアトラクトが上手なCOOやCFO、人事担当役員が出てきて対応するケースもあります。「最初から社長が出てこなかった」と候補者ががっかりする必要はありませんし、実際、その方がスムーズに話が進んでいく場合もあります。
要するに、CXO採用において重要なのはアトラクトの巧拙です。CXO候補になるような人材は非常に忙しく、かつ他にも魅力的なポジションを提案されていることもあり、その中から厳選して「まずは会ってみよう」とスケジュールを調整しています。
そのためCXO採用では初回面接が非常に重要で、ここで上手にアトラクトできないとその時点で話が終わりになってしまいかねないのです。
経営幹部のオープン採用でCEOが初回面接に出る理由
一方、最近増えているのが経営幹部のオープンポジション採用です。これはあらかじめCFOやCIOなどのポジションを決めず、広く経営幹部を任せられそうな優秀な人を探して採用しようとするものです。このケースではCEOもしくはそれに準ずる立場の人が初回面接に臨む必要があります。
急成長中の会社では、必ずと言っていいほど経営幹部人材が足りていません。これはスタートアップだけでなく、すでに上場している企業でも同様です。そこで必要とされているのは既存のポジションを埋める人材に留まらず、「こんな人材がいたら新たにこんな展開ができる」という、経営ニーズを満たす人材です。
時価総額数千億円規模に達しているあるメガベンチャーでは、私たちが経営幹部候補として推薦した人とはCEO自ら一次面接に臨みます。超多忙なCEOがいきなり候補者と会う理由は、頭の中にある抽象度の高いさまざまな経営イシューを任せられる人材を真剣に探しているからです。
そして優秀な人材と出会うとその人の可能性を見定め、 「この人がうちにジョインしてくれたら、こんな業務を任せられる」、「新たにこんな展開ができる可能性が生まれる」と考え、その候補者から発想してポジションを作ったりアサインしたりしていきます。
ポジションありきではない、抽象度が高い経営幹部のオープンポジション採用は、企業全体を俯瞰して見ている立場の人でなければできません。すなわちCEOやそれに準ずる立場の人でなければできないので、自ずと初回面接からCEO自ら出るようになるのです。
とはいえ、ここでお伝えしたいのは、「オープンポジション採用」そのものが良いというわけではありません。これまでのコラムでも、経営課題やミッションが曖昧なまま「優秀な人がいたら」という依頼は、結果的に企業にとっても候補者にとってもミスマッチになりやすいとお伝えしてきました。
ただし、今回お話ししているようなケースは、ポジションは未定でも、経営としての課題や今後の方向性が明確にある状態です。だからこそ、候補者の強みを見て「この人ならこういう役割をお願いしたい」と具体的に落とし込んでいけるのです。
つまり、ただの「何でもいいから優秀な人を」というオープンポジションではなく、「経営のリアルな課題に紐づいたオープン」であることがポイントです。
(2025年8月7日)