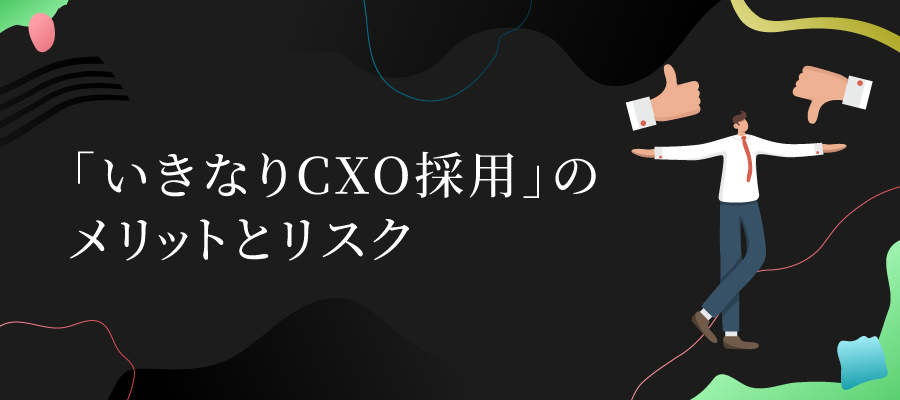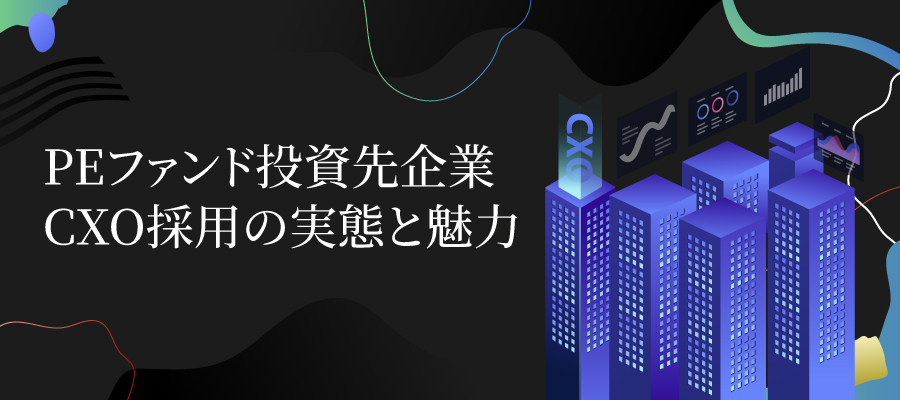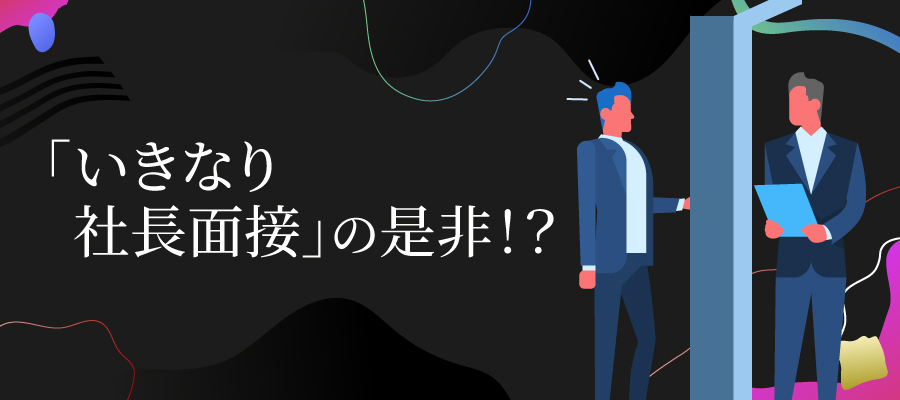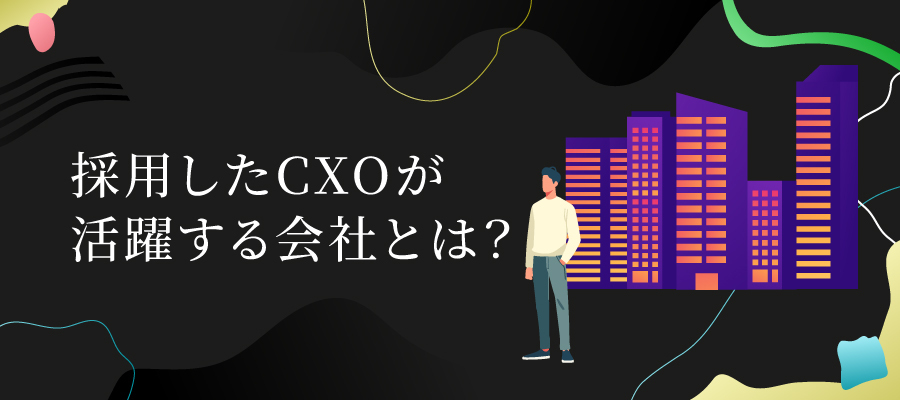会社を飛躍させるCXO採用はどのようなものか
最初からCXOなど経営幹部ポジションで採用した人材が活躍し、その会社の飛躍に貢献することがスタートアップ企業にはよくあります。
たとえば、知名度の高いスタートアップやメガベンチャーのCFO経験者が入社して、海外の有名ベンチャーキャピタルからの資金調達を成功させ、成長の加速に貢献した。あるいは、もともと独自技術が売りでマーケティング部門がなかったベンチャー企業に大手消費財メーカーのブランドマネージャーが入社し、BtoC事業を開花させた——。
こうした事例は多々ありますが、「いきなりCXO採用」は常に有効かというと、うまくいかなかったケースもまた枚挙に暇がなく、その会社の経営に大きなダメージを与えてしまうケースもあります。
今回は「いきなりCXO採用」の是非について考えてみましょう。
いきなりCXOや幹部採用をしなくても成長している会社はたくさん存在するので、絶対にしなければならない施策ではないと思います。ただし前述したように、幹部ポジションで採用した人材が会社の飛躍的な成長をもたらすことがあるのもまた確かです。
とくに事業の成長が加速しているスタートアップ企業では、経営幹部の採用がうまくいっていることが多いです。逆に戦略やビジネスプランが秀逸でも事業が成長していない会社では、優秀な人材を採用できていないケースがよく見られます。
こうした点を踏まえると「いきなりCXO採用」は大いに有り、といってよいでしょう。
では、「いきなりCXO採用」の成功と失敗を分けるポイントはどこにあるのでしょうか。一つ大きな要素が、その経営幹部ポジションが本当に必要で、役割がきちんと定義されていることです。
たとえば、多くの企業がDXに取り組んでいる中で競合に対しDXで後れを取り、かつ社内にDXを推進する人材がいない会社で、他社でDXの実績がある人材を幹部レイヤーで採用するケース。このように明確な課題がある場合、社内のメンバーの納得感も高いので、よい結果が得られやすくなります。
また、まったく知らない人を採用するより、CEOや経営幹部が過去、一緒に働いたことがあり、能力や実績を十分に把握している人をリファラル採用したほうが、うまくいきやすいです。幹部採用の失敗は大きなダメージをもたらすことがあるので、そうしたリスクも低くなります。
「いきなりCXO採用」に必要な「覚悟」
逆に失敗しやすいのは、ネームバリューに惑わされるケースです。スタートアップ企業が資金調達能力やIPO実務に期待して、CFO候補として外資系投資銀行出身者やPEファンド出身者を採用しようとすることがありますが、実際には事前の期待に応えられないケースがよく見られます。
これは幹部採用に慣れていない会社が起こしがちな失敗です。過去の勤務会社や肩書に目を奪われて、その人の詳細な実績やカルチャーフィットを十分確認しないで採用すると、こうした事態が起こりやすくなります。
ただし、採用した人材が優秀で実績十分でも、期待した成果が出ないケースもあります。新規事業を5つ始めたとしても、すべて軌道に乗らないほうが普通でしょう。活躍できるかどうかは、必ずしも個人の能力だけでは決まりません。
そもそもCXO候補者のことを知り尽くし、本当に活躍できるか確信を持つには、1年以上一緒に働かないと無理な話です。会社の成長フェーズが変われば、必要な人材も変わってきます。そうなるとできる限りその人のことを知った上で、失敗する可能性も踏まえながら、経営者がどこかで思い切って採用を決断するしかありません。
ここで二の足を踏ませるのが日本の解雇法制です。もしCXOとして採用した人が活躍できなかった場合でも簡単に解雇はできないため、日本企業ではCXO採用に慎重になりがちで、あまりチャレンジしないのです。これでは人材をてこにした飛躍的成長は望めなくなってしまいます。
しかし、実際にはその人が本当に優秀な人物で、適切なプロセスを踏んでいけば「今、私はお役に立てていないですね」ときれいにお別れすることが可能です。
当社の紹介であるオーナー企業にCIOとして入社した方が2,3年間活躍した後、その会社の成長フェーズが大きく変化したことがありました。
「これまでのあなたの仕事にはとても感謝しています。しかしこれからのフェーズには、別の力が必要になりました」
オーナー社長が率直にそう伝えると、CIOは「わかりました。あなたに直接引導を渡していただけるなら本望です」といって退職していきました。その後、この方は別の会社のCIOを務め、現在は大手グローバル企業のCIOとして活躍されています。
CXOとして採用した人材と何らかの理由でお別れしなければならない時、経営者がきちんと引導を渡す覚悟があるかどうか。CXO採用に挑戦するなら、これを事前に考えておく必要があります。
(2025年6月20日)