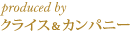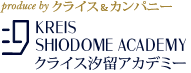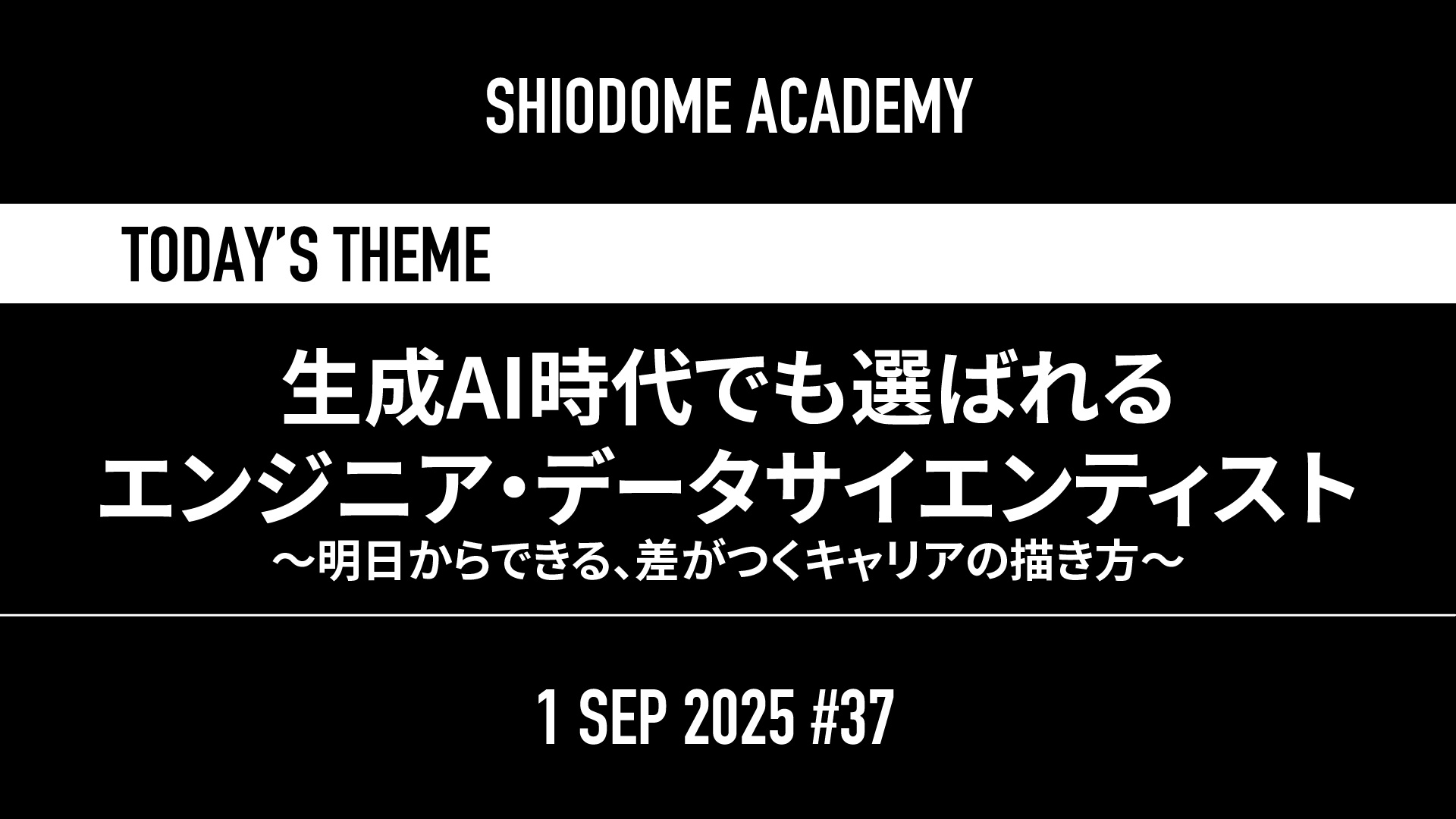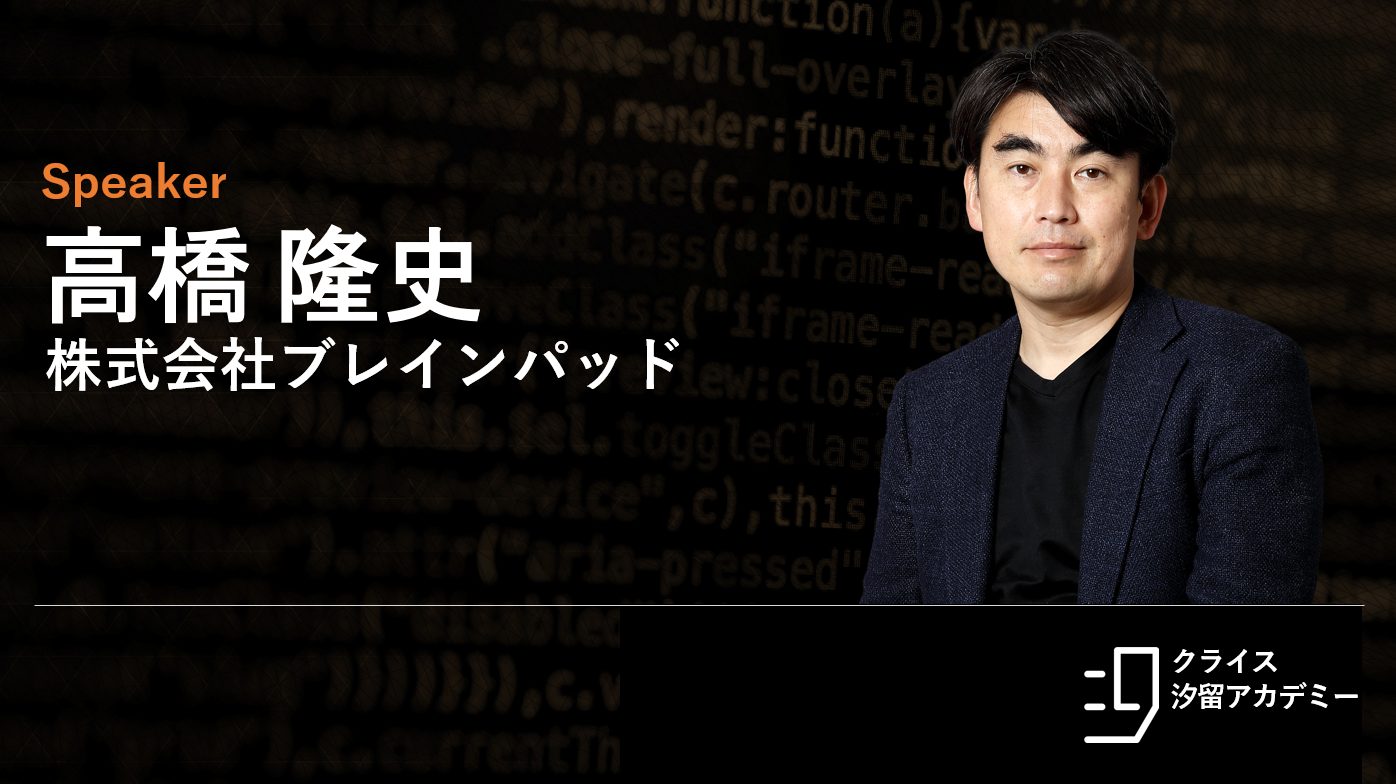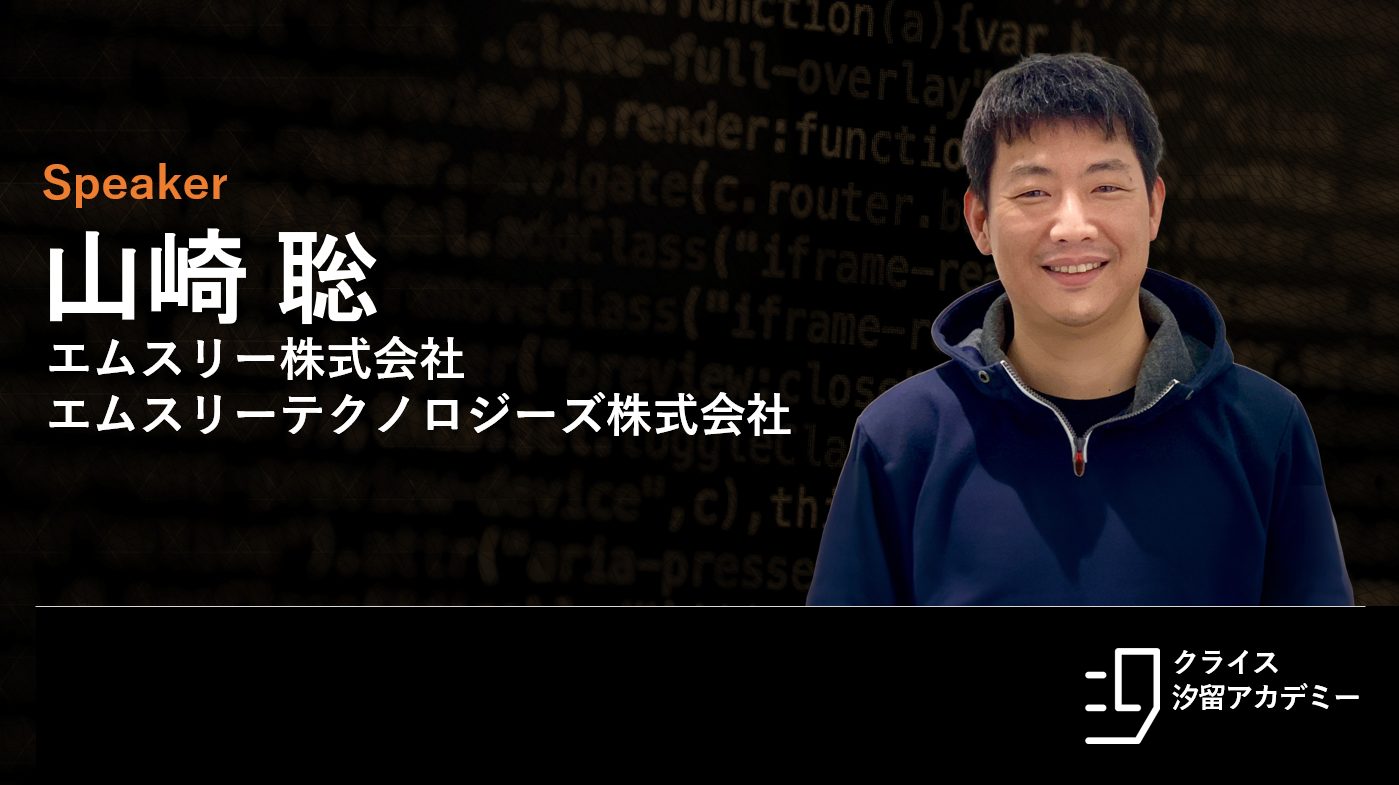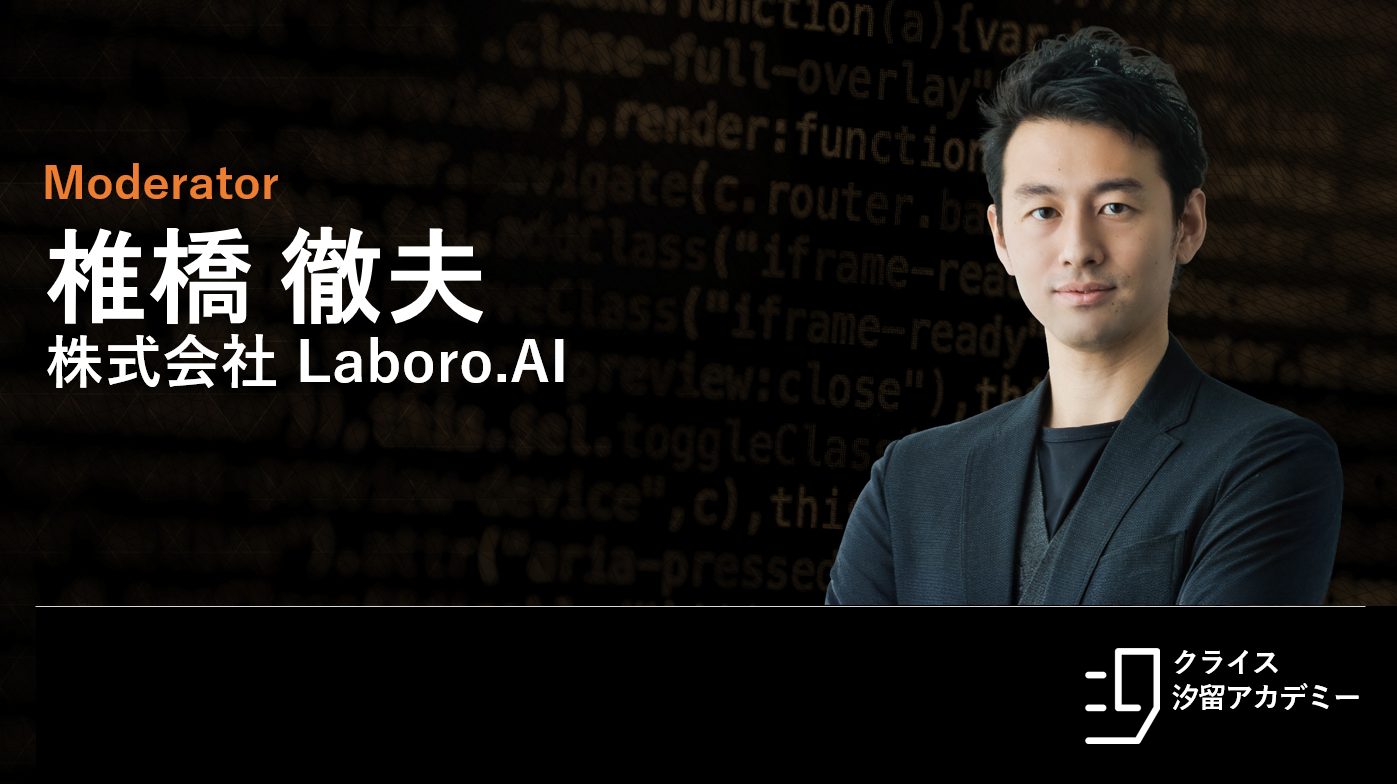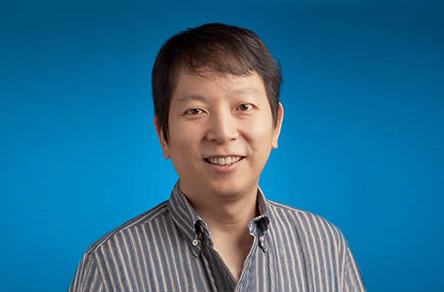2025 Sep
01
Mon
セミナーレポート
生成AI時代でも選ばれるエンジニア・データサイエンティスト ~明日からできる、差がつくキャリアの描き方~
高橋 隆史氏 株式会社ブレインパッド 取締役会長 Co-Founder
山崎 聡氏 エムスリー株式会社 取締役CPO / CAIO,エムスリーテクノロジーズ株式会社 代表取締役
椎橋 徹夫氏 株式会社 Laboro.AI 代表取締役CEO
Contents
パネルディスカッション
-
※今回の汐留アカデミーは、以下のアジェンダで登壇者によるディスカッションが繰り広げられました。
■生成AIで何がどう変わったのか?今後予想される変化は?
■選ばれ続ける人と取り残される人の違いとは?
■明日からできるアクションプラン(育成事例、アドバイス)
■質疑応答
本セミナーレポートでは、当日の内容から一部抜粋してお届けします。 - 椎橋
-
企業や組織のあり方が根本から変化していく中で、「人材」「タレント」に視点を置いたとき、「選ばれる人」と「取り残される人」の違いはどう見えますか?
- 高橋
-
いまは技術がどんどん変わります。とにかく触って、使いこなし、いじり倒すくらいでいかないといけない。つまりAIを使う側に回ることが重要です。
そのうえで、トライし続ける・実際に使いこなす・仮説検証を行い、評価できる人に回る、この経験値を蓄えることが大事だと思います。今、AIツールで生産性を上げられるのは、その業務において既に一定の評価・判断能力を持っている人で、そういう人が他人に作業を頼まずAIツールを使って自分で仕事をするようになっている。一方、作業を振ってもらって仕事を覚えている過程にある人からは、自分の仕事が奪われているように感じられる面がある。こういう人材にどうやって早くAIの出力を評価できる側に上がってもらうか、これが企業が今後抱える大きなテーマです。
しかし、とにかく、個人としては、まずは自分でAIを使いこなすこと。そのうえでどう実装し、ビジネスにどうつなぐかという視点が重要です。これまではエンジニアやデータサイエンティストにとって、振られた仕事をこなすだけで評価される場面もあったかもしれませんが、今後は「ビジネスに成果をつなげてナンボ」という発想がより求められる。そのマインドを大前提に行動し続けることが重要だと思います。
- 山崎
-
生成AIの使いどころは大きく2つあります。1つは、個人の仕事の生産性を上げること。もう一つはサービス・プロダクトに組み込むことです。
先ほど高橋さんが仰った通り、使いこなすのは大前提です。苦手・使えない人は取り残される。競合企業も新しく入ってくる人たちも頑張っているからです。
私は新卒とも話しますが、彼らは生成AIネイティブです。これからの若い世代は小中高大を通じて慣れ親しんでおり、レポート作成や確認はもちろん、あらゆることを生成AIで効率化していく。だからこそ使いこなすことは大前提で、むしろリードできる・教えられる・組織化できるところまでできる人が重宝されると思います。
次にプロダクト組み込みも当たり前になります。バックエンドでLLMを使い、認証トークンを発行してAPIをたたく、このくらいは息を吸うようにできないと厳しい。
しかもそれだけでは足りない。自社のビジネスを伸ばすために、どこにLLMを使うべきかを意思決定できなければならない。プロダクトマネジメント的な発想が必要で、PMがやりたいことに対して、エンジニアリングではどこまででき、どの程度のコストがかかるか。そうした現実的な判断をリードできる人でないと、生き残るのは難しいかもしれません。 - 高橋
-
私はデータサイエンティスト協会の代表も務めていますが、現在、生成AIの普及を前提に「データサイエンティストの定義をどう更新するか」という議論を進めています。方向性としては、上流や横断で価値を作る力がより求められる。従来からサイエンスの力・エンジニアリングの力・ビジネス力の三本柱と言ってきましたが、今後は領域を融合させて価値を出す力がなければ新しい時代のリーダーシップを執れない、という議論です。これは広い意味ではデータサイエンティストに限らずエンジニアにも同じことが言えます。生成AIがすっかり景色を変えてしまいました。
勿論、将来を完全に予見するのは難しい。ただ確実に言えるのは、AIをパートナーかつ先生にして成長できる人は強いということ。AIを壁打ち相手にして、質の高い思考実験を繰り返せる。AIは仕事を奪う存在とも言われるが、使い方次第で自分の能力を引き上げる存在でもある。代表例が、将棋の藤井名人。コンピュータ将棋に人間が勝てなくなって久しい中でも、逆にAIをフル活用して対人間で圧倒的に強くなった。この進歩を自分の成長に向けることが非常に大事だと思います。
経験を積んだ先輩層がAIで生産性を上げるなら、若く吸収力のある人は生成AIを追い風に急速に能力を伸ばす。上手くすれば技術的なキャッチアップは加速的にでき、追い抜くこともできる。勿論、その一方で、時間がかかる「ビジネス理解・人間理解・社会理解」にも取り組むことが重要だと思います。
- 椎橋
-
ここまでの流れを踏まえた「明日からできるアクションプラン」について、具体的に何をやればいいか、アドバイスがあればぜひお聞かせください。
- 山崎
-
2つあります。
1つ目は、AIに対して食わず嫌いをやめることです。時代の流れは不可逆で、AIがなぜこれだけ注目されているのかを、体験を通じて理解することが大事です。そして限界も感じてほしい。「この作業は難しいけど、これはできる」と見極めることです。
例えば生成AIを使ってみると、一発で綺麗なコードを出力するのは難しいけれど、手直ししていけば使えるレベルになるのか。テストなら自動生成で良い結果が出せるのか。自分で書くのが面倒で後回しにしていたものをAIに作らせる、そんなところから始めればいいと思います。とにかくAIに対するアレルギーをなくすことが、生き残る可能性を高めます。
2つ目は、会社全体がAIにアレルギーを持っている場合、経営者にAIを使ったデモを見せることです。自分は進めたいのに会社が乗り気でないときは、経営陣を味方につける必要があります。私がよく使うパターンは、VercelのV0(v0.dev)というサービスです。エンジニアやデータサイエンティストは黒い画面が大好きですが、その凄さを経営陣に言葉で説明しても伝わりません。
そこで経営陣に対し、V0を使って「15~30分でこれほどすごいサービスが作れる」というところを画面共有で実演するんです。私もグループ会社で「AIでできることがピンと来ない」という方に対して、Zoomでつないで、その人の担当領域に関わる新しいサービスをV0でゼロから数分で作って見せたことがあります。すると感動して価値観が変わるんですね。
要するに、生き残れる環境を自分で作っていくことが非常に大事です。そうでなければ最後は転職という選択肢になるかもしれません。ですから、自分でチャレンジすることと経営陣を味方につけることは、すぐにでもやったほうがいいと思います。
- 椎橋
-
なるほど。自分が変わるだけでなく、環境が変わりにくいのであれば、それも変えていくべきだということですね。
- 山崎
-
はい。そのくらいしないと生き残れないかもしれません。
- 椎橋
-
ありがとうございます。では、高橋さんの「明日からのアクションプラン」についてはいかがですか。
- 高橋
-
私もほぼ山崎さんと同じです。まずはAIに対するアレルギーをなくしましょう。会社が費用を払ってくれないなら、個人で有料プランを払ってでもフルで使ったほうがいい。最先端のものを使うことで、生成AIにできないことが分かるし、バージョンアップのたびにできることが増えることも実感ができます。この数年の進化のスピードを体験すると、期待値も危機感も高まります。
今は誰もがフロンティアに立てる環境がある。昔はビッグデータを扱いたければGoogleやYahoo!に転職しないと触れられなかったのに、今は最先端の恩恵を安い価格で受けられる。非常に恵まれた時代です。本人のモチベーション次第で最先端に触れることができますし、ノウハウや使い方の情報もどんどん公開されている。前向きさ次第で成長角度を大きく変えられる。だから、その恩恵を最大限取りに行くことが重要です。
もう1つは自己分析です。自分が今どのステージにいるのか。開発や分析において、評価や判断まで経験を積めていないなら、今後そうした機会が急速に減っている前提で考えて、今ある数少ない場をものにする。あるいはお伝えしたようにAIをパートナーにして学習する。
さらに働く環境の分析も必要です。変化にチャレンジさせてもらえる環境かどうか。日本の企業はIT投資が十分でなかったため、データが揃っていない会社がまだ多い。過去の投資が不十分だと、AI活用の恩恵を十分に受けられないケースもある。経営者の理解が大事なのはもちろんですが、それ以外の環境要因もあります。どうしようもなければ転職もオプションになると思います。
- 椎橋
-
お二人のお話で面白いのは、アクションプランというと今できる戦術的なことに目が向きがちですが、技術が急速に進化し社会も変化する中で、自分や環境を俯瞰して戦略的に考える重要性を強調された点です。
- 山崎
-
技術の転換点では毎回同じことが起こっています。インターネット登場のときも、電話回線を直接扱うのか、インターネットを扱うのか、そもそもネットワークを扱わないのかという議論がありました。スマホが出てきたときも同じで、ガラケー向けのゲームサイトを作っていたが、スマホ向けは作らないのか、という話がありました。
だから新しい技術が出てきたときにどう関わるか。転職が手っ取り早い場合もあるし、自分で触ってみるのが手っ取り早い場合もある。
- 椎橋
-
新しい技術を取り込んでキャッチアップしていく一方で、変化が速いからすぐに陳腐化してしまうのではないか。でもキャッチアップしなければ置いていかれる。このとき、何をキャッチアップし、何は捨てるべきか、どう見極めればよいか。これは個人的にもよく思うのですが、いかがでしょうか。
- 山崎
-
私の場合は、当時「PalmPilot」というPDAが好きで、Palmwareというアプリを書いていました。それは見事に陳腐化しましたが、確実にその後のためになりました。
結局は性格にもよると思います。アーリーアダプターとして新しいことに挑戦するのが好きなのか、枯れた技術で十分だと分かった時点で後から乗るレイトマジョリティ型なのか。これは好みです。
あまり見極めにこだわらず、どんどん触っていくことです。結果的に陳腐化するものもあれば、長く残る技術もある。30年や50年のスパンで見ればほとんどの技術は陳腐化します。そのサイクルをどう捉えるかです。
ITの世界で10~20年使える技術は珍しい。iOSも最初はObjective-CでしたがSwiftに変わった。AndroidもJavaからKotlinに変わった。同じプラットフォームの上でも技術は陳腐化していきます。だから陳腐化を怖がる必要はないという考え方もあります。
- 高橋
-
確かに技術は陳腐化します。でも、だからといってキャッチアップを怠ると、その技術を積極的に取り入れて伸ばした競合に負けてしまうんです。だから「やらない」という選択肢は、少なくとも会社レベルではあまりありません。それに、技術的に上限が見えていても、新しいものにチャレンジする行為に優秀な人は引き寄せられる。新しいことに挑戦するリスクを許容する人材が集まり、一定の確率で成功する。
一方でやらずに待っていると、挑戦する会社に機会を奪われて打席に立てなくなる。だから会社レベルではチャレンジを続けるし、個人レベルでも考え方は同じだと思います。もし、明らかに自分のやりたいことにつながらないと分かっているなら無理にやる必要はないと思います。
ただ、今起きているのは作業生産性を上げる技術トレンドで、何をするにしても生産性を上げなければ成果を出すスピードが変わってしまう。ですから、今の段階では使わないという選択肢はないのではないでしょうか。
LLMをゼロから自作するのは実効性が低いと思いますが、今の変革の基盤技術なので、それがどう動いているかを理解し、どう使うか、現時点での限界を理解することは非常に大事です。
- 山崎
-
この話のポイントは、競合企業が必ず存在するということです。
- 高橋
-
そうなんです。
- 山崎
-
ライバルは必ずAIを利用してきます。さらに採用の競合にもなります。そういう会社に人が集まってしまう。日本のエンジニアも優秀な人ほど海外に転職してしまうことがあり、今後それはさらに激しくなるでしょう。日本の経済力が弱まっているため、魅力的なオファーがあれば会社が空洞化して優秀な人から抜けていく。
だからこそ、技術を使って生産性を上げ、付加価値を増やし、稼いで良い給料を払える会社であり続けなければ人材を維持できなくなる時代です。
作業生産性が上がれば、アイデアが市場に出るまでの時間が短くなる。数を出せばどこかで当たって業界が変わってしまう。だからこそ、緊張感を持って能力を高め続ける必要がある。
また、競争や相対的な立ち位置を意識することが重要です。多くの企業とAI活用に取り組んでいると、「進化が速いから、今は待つ」と考える人は一定数います。でも待っている間に競合は今あるものを取り入れて先に進んでしまう。
大手で安定している企業ほど「待てばいい」となりがちですが、それは危険です。個人のキャリアにおいても、待っている間に隣の人はどんどん前に進んでしまう。この点は非常に重要だと思います。
クライス汐留アカデミーは今後も定期的に開催して参りますので、ご興味あるテーマがございましたら是非ご参加ください。
(オフラインへのご参加は、弊社にご登録されている方を優先させていただくことがございます。ご了承ください)